木の家具、特にテーブルを見ていると
たまにリボンマークが入っていることありませんか?

これは「千切り(ちぎり)」と言います。
家具木工用事典には、
「木部の接合の際、補強のために埋め込む鼓(つづみ)形の板片。
両端が広く、中がくびれて狭い。【衽】や【乳切木】とも書く」
と記されています。

例えば、こんな感じで割れてしまった箇所は、

割れ部分を樹脂で埋めて、千切りを入れることで
さらなる割れを防ぐ役割を果たしています。

この千切りは、割れではなく傷を隠すために入れています。
もちろん、割れや傷以外で使用されることも。

この照明のどこかに、千切りが入っています。
お分かりになりますか?

答えはここです。
木材を繋ぎ、強度を高める役割を果たしています。
見えない場所に千切りが入っていることもあります。

天板の裏側。
左右の板を繋ぐ役目を果たしています。
こんな感じで使われている千切りですが、
割れや傷に対して使用されている千切りは
総じて色が濃いことにお気づきになりましたか?

そうした部分に使われる千切りには、
広がりの進行を防ぐため、硬い木である必要があります。
その役割に適しているのが
「黒檀(こくたん)」という木です。
私たちの身の回りでは
ピアノの黒鍵や判子として使われています。

名前の通り、黒に近い濃い色合いをしているため、
千切りが濃い色になる、というわけです。
また千切りを見かけるのが、
一枚板に多いわけとしては、
生産方法に違いがあるためです。

通常のテーブルは、何枚かの板を繋ぎ合わせて
一台のテーブルになります。
もし千切りを入れないといけない板があれば
別の板に替えれば済む話ですが、
採るまでに100年以上かかる一枚板はそうはいきません。
なので、千切りは一枚板や一点もののテーブルで
よく見かけるというわけです。
このように、千切りの本来の役割は補強材としてですが、
デザイン性があるので、アクセントにもなります。
現に、この千切りをデザインとして天板に入れてほしい!
という、お話をたまにいただくことがあります。
自然の魅力を活かした人間の知恵として千切りを見ると、
それもまた「味」となるかもしれません。

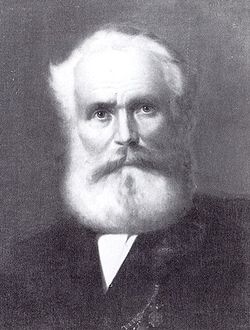
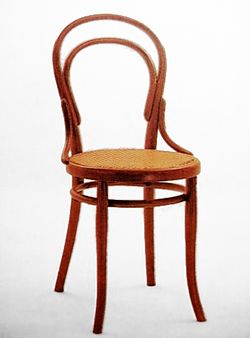





















 <ビーチ材>
<ビーチ材> <椎材>
<椎材>