2月に入り、日が延びてきたことを実感している今日この頃ですが、まだまだ厳しい寒さが続いています。
さて、寒さとセットでやってくる「乾燥」。そしてこの「乾燥」によって頻度が高くなる、バチッという「静電気」。私もこの時期は車のドアに触れる度に痛い思いをしています。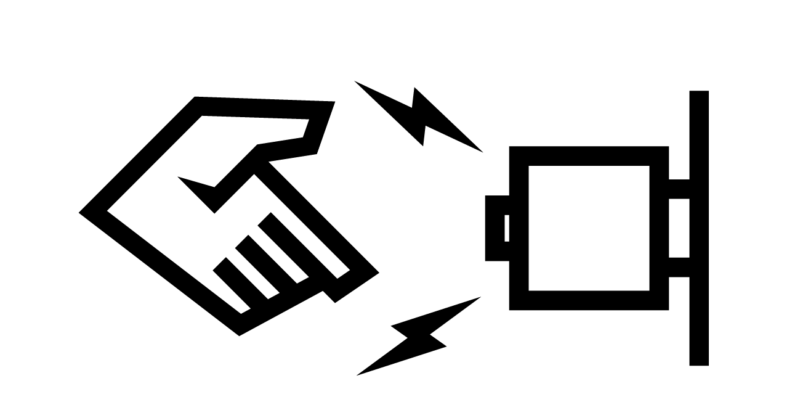
ご存知の方も多いかと思いますが、この「静電気」、冬に多く発生するのは「乾燥」が大きく関わっています。私たち人間の体には電気が流れています。この体内の電気、湿度が高いと、空気中の水分を介して体外に逃げていきますが、「乾燥」していると、体の中に溜りがちです。それが金属など、電気を通しやすいものに触れると一気に放出され、バチッと痛い思いをさせられるのです。
そこで登場するのが「木」です。「木」は、電気をゆっくりと流して放出するため、あのバチッと痛い思いをすることなく、体内の電気を逃がしてくれます。私もBRUNCHで毎日木の家具に触れるようになってから、マフラーを外す際の髪の毛のパチパチや、ドアノブに触れた時のバチバチが減ったと実感しています。「木」にはリラックスなど、癒しのちからがあるとも言われていますが、静電気除去にも役立つなんて、木の家具を生活の中に取り入れると良いことがいっぱいですね。

とはいえ、木の家具達も「乾燥」は得意ではありません。「乾燥の季節がやってきます。」でもご案内していますが「乾燥」は、天板の割れや反りの原因となります。加湿器などで湿度を保てば、木の家具の劣化も防ぐことができ、風邪予防にもなり、体内の静電気も放出される。湿度と仲良くしつつ、BRUNCHの木の家具達に触れて静電気を放出しながら、木のぬくもりに癒されて下さい。皆様のご来店をお待ちいたしております。






